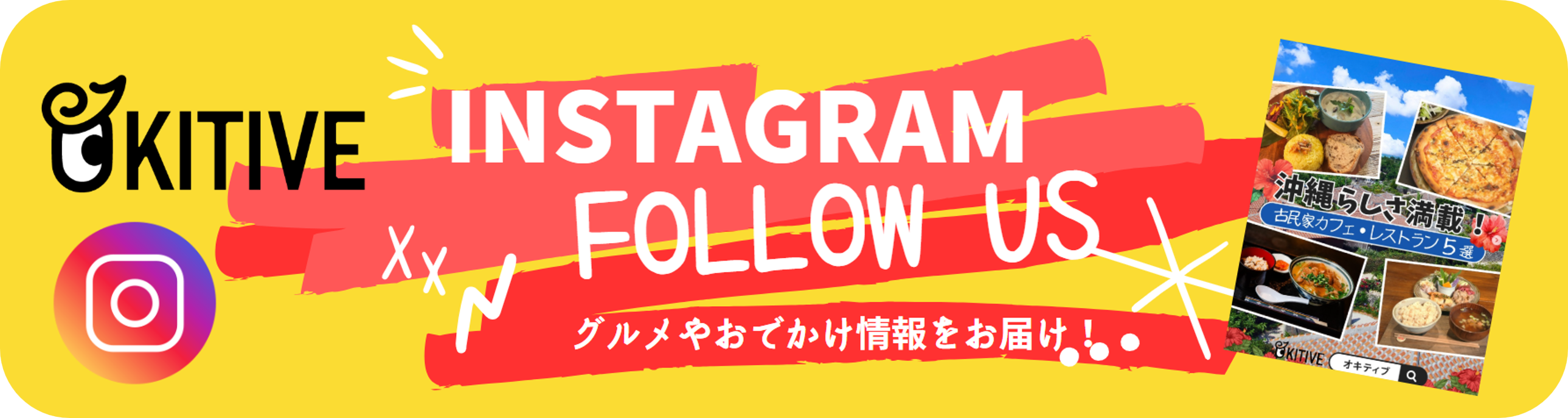沖縄戦の体験はゆるがない 宮崎の語り部・常盤泰代さんが伝えたい思い
宮崎県を拠点に、戦争や学童疎開について研究し語り部として活動する常盤泰代さん。
沖縄戦の歴史認識や平和教育をめぐり、国会議員が「無茶苦茶な教育」などと発言したことに胸を痛めています。
戦争体験者が語ってきた証言と二度と悲劇を繰り返さないという人々の強い思いが沖縄の平和教育を支ええていて、次の世代に残していかなければならないと訴えます。
常盤泰代さん:
平和教育をしている立場から、今心して取り組んでいかないと、これは大変だと思って背筋が伸びるような思いがしました
宮崎県に暮らす常盤泰代さん、元小学校教諭で、現在は戦争や学童疎開の語り部として活動しています。
戦後80年が経とうとしている中、戦争体験者が残してきた証言や史実をゆるがすような発言が乱れ飛ぶ現状に、改めて教育の大切さと恐ろしさを認識したと話します。
常盤泰代さん:
そういった発言、こういった感じの発言というのも、一つはその方の教育の上に立っていると思う。いろんな物事を解釈するときに、やっぱりベースにあるのは教育
およそ80年前、沖縄の地上戦から逃れるため6000人あまりの子どもたちが九州へと疎開しました。
そのうちおよそ3000人の学童疎開を受け入れた宮崎県。
常盤さんは自身が暮らす宮崎と沖縄のつながりに強い関心を持ち続け、これまで幾度となく沖縄の地を訪れてきました。
その度に、残されてきたたくさんの証言、遺品、史料などに触れ、沖縄の人々の手によって平和に対する思いが確固たるものとして継がれてきたのだと感じていました。
常盤泰代さん:
沖縄の平和教育というのは、長年先人たちが何とかして伝えなければいけないという思いがあって、いろいろなものを残していただいて、それを伝えようとする先生方の努力があってというのはすごく感じます
常盤泰代さん:
沖縄では、『沖縄県史』『市町村史』そういったものに戦争体験がまとめられているものがたくさんあります。その中から私は声を拾う。残念ながら宮崎には、戦争体験者の記録が極端に少ない。沖縄には記録を残そうという人たちの思いがたくさんいろんなところに込められている。教材として、考える一つの材料として、それらを使うことができているのではないか
多くの証言が残されている一方、戦争体験者の生の声が聞けなくなったとき、消えてしまう歴史があるのではないか、平和教育の説得性がどう保たれるのか、危機感を抱く常盤さん。
戦争体験者から直接話を聞けない世代も増えていく中で、常盤さんは精力的に学校現場に足を運び、子どもたちに「平和とは何か」と問い、ともに考え続けています。
常盤泰代さん:
私が一番怖いのは「無関心」ということです。「何の話しているの?」関心がない、知らんぷりをしているというのがとても怖い。戦争のときに、またはこれまでに、一生懸命頑張ってくださった先輩方、先人たち、前を生きていてくれた人たちがいるから私たちの今の生活があるんだよね。みなさんも平和についてちょっと考えてみたらいいかなと思います
常盤さんは戦争の時代とこれからをつなぎ、そして沖縄と県外各地をつなぐ架け橋として力を尽くしたいと話します。
常盤泰代さん:
つなぐ人がたくさんいれば、広まっていくのかなと思いますし、自分がつなぐ人であったらいいなと思います
80年前に刻まれた悲劇と歴史に向き合い続けるため、常盤さんは2025年も慰霊の日に合わせて沖縄を訪れ、体験者の声、沖縄の声に耳を傾けます。
あわせて読みたい記事