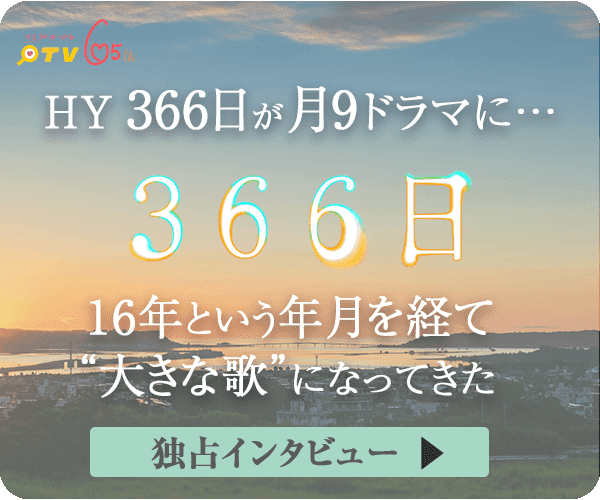沖縄の教職員の病休が全国ワースト 厳しい労働環境を経験者が語る
昨年度、県内で精神疾患によって休職した教職員は過去最多の229人ですべての教員に対する割合は全国ワーストが続いています。いま学校で何が起きているのかまた教員経験者が伝えたいこととは・・・。
地域のママたちが街の情報を発信するFMコザの番組「ママ夢ラジオ沖縄」。
この番組を去年立ち上げパーソナリティーも務める登川めぐみさん。
旧姓(渡慶次さん)にちなんで「とっけー」というニックネームで呼ばれています。
とっけーさんはおよそ10年間、公立の中学校で英語教師として勤めてきました。
公立中学校に勤務していたとっけーさん
「(中学生は)親に言えないことを抱えている子がほとんど、それを学校生活でみながら、声かけた時にだんだん明るくなったり変わっていったりすると、やりがいを感じた」
生徒の成長に喜びを感じていたとっけーさん。しかし5年前、過労のため心身に不調があらわれやむなく休職しました。
公立中学校に勤務していたとっけーさん
「担任をもって、自分の研修もこなしながら、部活動もあるし、終わらない業務にいつまでも追われている感じが初任の頃から感じていて。自分が結婚して自分の子どもができたときに、この仕事と家庭を両立することが苦しくなって、その時にかなり限界は感じた」
日々業務に追われる中で我が子に向き合うこともできなくなり、長く心療内科にも通いました。
公立中学校に勤務していたとっけーさん
「すごく自分の中でのバランスが崩れていって、覚えていない、当時のこと」
文部科学省の調査によりますと昨年度県内で精神疾患で休職した人は前の年度より30人増えて229人と過去最多を更新。
全教諭に占める割合は1.45%と統計を取り始めた2018年度から5年連続全国ワーストが続いています。
先生たちが追い詰められる背景にあるものは1971年に制定された「給特法」だと指摘されています。
教職員には時間外労働の手当てを支給しない代わりに給料の4%に相当する額を上乗せすることを定めていますが、現代は実態と合わなくなってきているのです。
琉球大学の西本教授は教育現場におけるコスト意識の欠如が教員の負担増加の原因にあると指摘します。
琉球大学大学教育センター・西本裕輝教授
「50年間、先生たちの業務は増え続けている傾向にありました。無限大に膨らんできている業務が、沖縄だけでなく全国で限界に達して先生たちが倒れ始めている」
給特法の改正に向けて文部科学省は検討を進めていますが、不足する人員を補うことも喫緊の課題となっています。
県教育委員会は今年度教員採用試験の受験資格を緩和するなど新たな人材を掘り起こす施策を打ち出しました。
さらに国の委託を受けてメンタルヘルス対策検討会議も立ち上がっています。
しかしこのメンタルヘルスへの具体策は現場に示されておらず、「いま病気で休職している人や育児休暇中の人が安心して戻れる環境の整備を急いでほしい」ととっけーさんは訴えます。
公立中学校に勤務していたとっけーさん
「今、最前線で必死で子どもたちと向き合っている先生たちも苦しめるし、戻る場所がない先生たちも苦しめるきっと新しく入ってくる人たちも教えてもらう時間もない。余計に離職者が増えてくるのではないかなと思います」
今は自分自身と家族を大切にしたいと教職を一度離れることを決断したとっけーさん。
新たな一歩として始めたラジオ番組のメンバーは元教員や小学生の子を持つ保護者もいて、いまの学校の現状について本音で話しあえる場となっています。
元小学校教諭
「全然楽しくない、闘いに行く気持ちで行っていたから、それって私が子どもに見せたい姿じゃないなと思った」
小学生の保護者
「先生たちがこんなに大変な思いをされているというのを全然知らなかった。最近お話聞いたあと、行動に移しているのが、なるべく学校に顔を出しにいくこと」
公立中学校に勤務していたとっけーさん
「一番犠牲になるのは子ども。それだけは避けたいと思うのは保護者も先生は一緒。先生たちに余白がないのであれば、保護者に現状を知ってもらう。それで今自分達ができることは何かと考えるだけでも変わる」
先生の気持ちも親の気持ちもわかる自分ができることは何か。とっけーさんは探ってきました。
コーチングやカウンセリングの資格を取得し、今後は先生たちが楽しく働ける職場づくりの講師として活動したいと考えています。
公立中学校に勤務していたとっけーさん
「私が今まで経験してきたことと、いま頑張って働いている先生たちへメッセージ。自分ができることはないか思っている」
あわせて読みたい記事