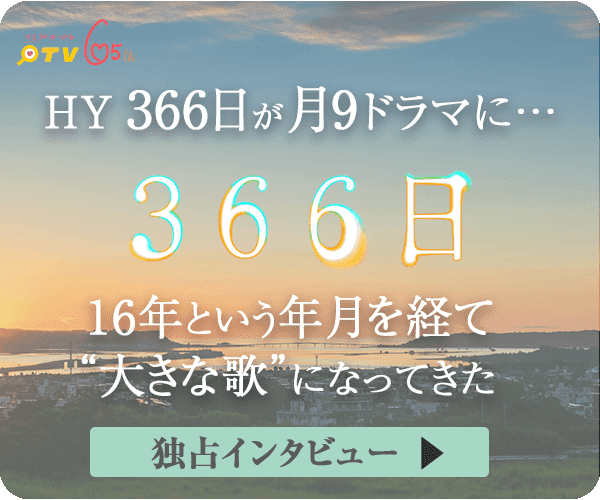「あなたにとって不要なものは誰かにとって必要なもの」 ジモティー×自治体 ごみ削減の取り組み
暮らしから考えるSDGs。年々増える粗大ごみの量を減らそうと嘉手納町では家庭などから出る不用品を捨てずにリユースする仕組みづくりに取り組んでいます。
必要なものを必要な人に届け、資源を循環させるその方法とは?
お目当ての品を求めて、遠く離れた豊見城市から利用者がやってきました。
「もうこれこれ、これですもうまさにこれです。これ探していたものでずっと。母親がちょっと体が不自由で、なかなか自動で回るっていう機械がなくて、これはもうまさに理想的な機械なので」
嘉手納町産業環境課環境衛生係・山城久幸係長
「(利用者は)安く手に入ったから喜んでくれるし、僕らは処分費用掛からないし(譲る方は)処分費用、運搬費用もかからない。もう1石で4鳥、確実に取れているので良かったです、本当に」
そう話すのは、嘉手納町役場で町内の廃棄物処理などの業務を担う山城久幸さん。
町役場の地下スペースにはリサイクルショップさながら、ベッドや冷蔵庫、オーブントースターなどが並んでいます。
これらは全て町民から集められた不用品です。
2020年度に嘉手納町で処分した粗大ごみの量はコロナ下の巣ごもり生活で家具や家電の買い替えが進んだことを背景に、5年前と比べると2倍以上に増えました。
※2015年:約87トン2020年:約189トン
読谷村と共同で運営するごみの処分場は老朽化が進み施設の維持・管理に多額の費用が掛かるほか、ごみの埋め立て地もおよそ10年後には満杯になる見込みです。
嘉手納町・山城久幸係長
「各施設ですね、延命化が必要だということで延命化を図るためにはどうするのか、簡単な答えがごみを減らす」
そこでごみを減らそうと嘉手納町が取り入れたのが、不用になった家具などを譲りたい人と譲り受けたい人をマッチングする地元の掲示板サイト「ジモティー」です。
ジモティーは現在、全国139の自治体と協定を結び、地域のニーズを元に不用品が循環する枠組みを共同で構築しています。
嘉手納町も2021年9月に県内で初めてジモティーと連携協定を結び、公式アカウントを立ち上げました。
嘉手納町・山城久幸係長
「(ジモティーの)周知を図って住民自らリユースの方をしていただくこと。あとは代理出品ですね、インターネット環境がないご家庭やスマホを使ったことがない高齢者の方々いらっしゃいますので、その方々を対象に代理出品の方をスタートさせた」
ネットに不慣れな高齢者などには町の職員が出向き出品のサポートや不用品の回収を行うことでジモティーの活用を促進していて、町全体でリユース意識を高めようと活動しています。
嘉手納町・山城久幸係長
「処分方法の中に捨てるではなくて、譲るという項目が一つでもそれぞれの方々に判断いただける状況になってきましたので、そこが一番良いところですね」
山城さんによりますと、これまでに代理出品した1100点あまりのうち、譲渡率は驚異の99.9%。
これまでは無料で譲っていましたが去年11月からは商品の状態に見合った価格を設定し売却するようになりました。
嘉手納町・山城久幸係長
「売却という形を示してその金額をまたさらに町民の方々に示して、より捨てるという方向から売ろうという売却しようという方向へ進んでいただけるのかなと思いまして」
得られた売上は町の歳入として、ごみの処分費用に充てます。
この日は地域の高齢者から回収の依頼があるということで同行させてもらいました。
町内でも特に高齢者が占める割合が高い中央区では、自治会長が役場と連携し不用品の回収に努めています。
嘉手納町・山城久幸係長
「レンジとオーブントースター、ミキサーや炊飯器、あとはヒーターですね。代理で自治会長のほうから問い合わせがあってまずは見に行こうと。そしたらやっぱり使えるものばかりなのでリユースしましょうと」
嘉手納町中央区・長嶺由次自治会長
「持っている本人にとってはいらないものでも必要な方にこのモノ自体が循環するというのは良い取り組みだと思っています。(高齢者の)皆さん喜んでいます」
職員が役場に運び込まれた不用品の状態などを確かめ、写真を撮影して掲示板に投稿します。
山城さんを中心にリユース活動を続けた結果、2021年度のジモティーとの連携による粗大ごみの削減効果はおよそ5.5トン。
町全体でも前の年度の粗大ごみの量と比べて、50トンあまりの削減に成功しました。
昨年度はさらに15トンの減量にも繋がり、過去5年で最少となるなど、町民のリユース意識は確実に高まっています。
嘉手納町・山城久幸係長
「目指すのはやっぱりリサイクル率の上昇ですよね。地球温暖化防止とかそういったものにもどんどん繋がりますので、まずはリサイクル率をせめて50%台に目指してやっていきたいと思います」
あなたにとってはいらないものでも誰かにとっては必要なもの。
行政と企業が一体となって循環型の社会を目指す取り組みはこれからも続きます。
あわせて読みたい記事