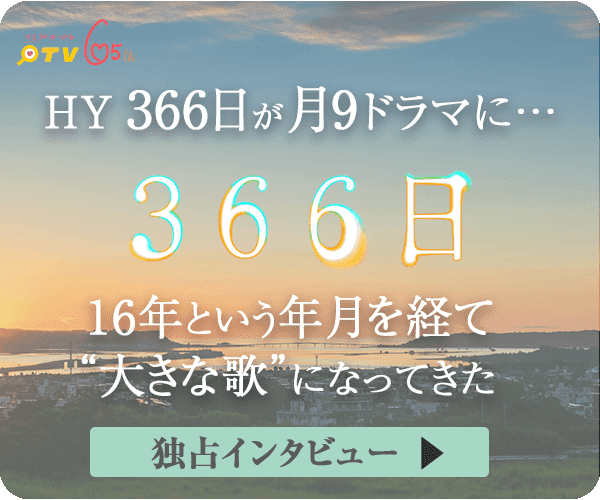”巨大な琉球漆器” 首里城ふたたび
2026年の完成に向け着々と再建が進む首里城正殿。長年にわたって首里城の漆の塗り替えや修繕に携わってきた漆職人が再建にかける思いに迫ります。
球王国の栄華を象徴する首里城。鮮やかな朱塗りから「巨大な琉球漆器」とも呼ばれていました。
漆塗り職人・諸見由則さん
「奉神門やって、それから瑞泉門やって、それから右掖門もやった」
伊平屋島出身で県指定の無形文化財「琉球漆器」保持者の諸見由則さん(63)。
首里城の塗り替えや修繕に携わって20年近くになります。
漆塗り職人・諸見由則さん
「沖縄のは難しい。本土は湿度が低いので漆の乾燥が徐々にしかいかないけど沖縄の場合はだいたい10分ぐらいで表面乾燥する」
繊細な漆は気温や湿度などに状態が大きく左右されます。
特に高温多湿の沖縄では本土に比べすぐに漆が固まるため、素早く仕上げる技術や天候を見極める知識・経験が求められます。
また漆は強い紫外線を受けると劣化してしまうという弱点がありますが、諸見さんはそれを補う沖縄独自の技法を用いています。
漆塗り職人・諸見由則さん
「木を保護するために漆があって、漆を保護するために油があるから、上の油だけを塗り替えすれば何年も持つということです。独自で作ってこっちで開発した油、本土にはないですよ」
古文書をもとに漆を紫外線から守る油を作り、その油と顔料を調合するという琉球王国時代に近い方法を再現しています。
漆塗り職人・諸見由則さん
「ただ好きだからですよ、でもその代わりいつも漆の事をずっと考えています」
「沖縄の職人でないと首里城は塗れない」そう自負する諸見さんは2016年から後輩達と共に首里城の正殿を塗り替えに着手。
2年3か月の年月をかけ鮮やかな朱色の城を蘇らせました。しかし、その矢先・・・
Q燃えている首里城を観てどんな気持ちだった?
「なんとも言えないね、燃えてショックはものすごくあるけど。はっきり言ってやるしかない。それと若い子たちをどんどん育てて、あと10年後20年後30年後も若い子たちがやれるように基礎づくりですよ。僕の場合はそうするしかない」
今回の再建では技術の継承と後継者育成に力を注ぐ諸見さん。
去年5月から始まった扁額の試作でも県立芸大や工芸振興センターの卒業生などを指導しています。
漆塗り職人・諸見由則さん
「首里城焼失、残念ながらやったんですけど、今がチャンスなのかなと逆に。いろんなものを経験させていきたいなと思っています」
若手の漆職人・崎間清野さん
「正殿にむけて携わっていきたいという思いがあるので、今少しずつ特訓してという感じで頑張っています。今はとにかく吸収していこうと思っています」
首里城の再建を通して琉球漆器の新たな道を拓きたいと話す諸見さん。というのも琉球漆器は生活様式の変化などで需要が減り生産額は大きく落ち込んでいます。
漆塗り職人・諸見由則さん
「育成していかない限り沖縄の漆器の将来はないと思っている。(首里城が)復元するということは沖縄の漆器がもっと今後伸びるものを持っていると思う、それにプラスして子どもたちが頑張っていけばいいんですよ」
諸見さんが塗る一筆一筆には首里城の再建と琉球漆器継承への情熱が込められています。
あわせて読みたい記事