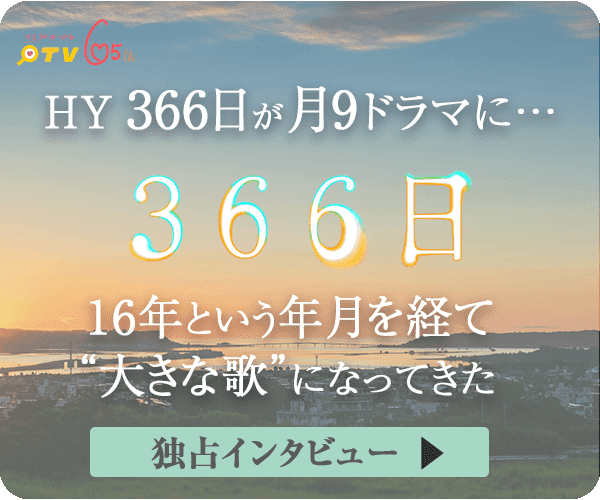沖縄で学びたかったこと ルワンダ虐殺を生き延びて
30年前の4月7日、アフリカのルワンダで起きた大虐殺=ジェノサイド。民族の対立によって100万人もの命が奪われました。その凄惨なできごとから生き延びた男性が沖縄を訪れ平和について語るイベントが開催されました。
「戦争は一夜にして始まりません」クロード・ムガベさん。アフリカ東部の国ルワンダで平和教育者として活動しています。クロードさんが8歳の時に起きた悲劇。それが大虐殺=ジェノサイドです。1994年の4月7日に始まった民族間の対立による殺害でわずか100日間で100万人もの命が奪われました。
「大虐殺で父親、妹、叔父叔母、いとこを含む65人の親類を失いました。」
今回の平和交流イベントは大学生らが企画運営を手がけたものです。クロードさんが沖縄を訪れるきっかけとなったのは読谷村のインターナショナルスクールを卒業し、今は大阪大学に通う山田果凛さんとの出会いでした。
起業家としても活動する果凛さん。4年前、コーヒーの取引のためにルワンダを訪れた際、ジェノサイドの実相を伝える記念館で、ガイドとして働くクロードさんと出会いました。
果凛さん「日本に行って沖縄に行って平和交流することが夢なんだよ」「わたし沖縄の高校生なんですよ」「じゃぼくの夢は叶うね」と言われたのが2020年の話。」クロードさんはなぜ沖縄を訪ねたいと思っていたのでしょうか?
講演の二日前、初めてアフリカ大陸を離れおよそ30時間のフライトを経てこの島に降り立ったクロードさん。早速向かったのは糸満市にある平和祈念公園と資料館です。
本村杏珠さん「うちなーぐち、ローカル・ランゲージ。うちなーぐちを使うとスパイ取り締まりと言って刑が科されました。」案内したのは果凛さんの呼びかけで集まった県内の大学やインターナショナルスクールに通う若者たち。79年前の沖縄戦で住民を巻き込む激しい戦闘があったことを説明しました。
下地隆仁さん「ガマはもっと暗くて遮断されている閉鎖空間でして、恐怖が蔓延して、アメリカの捕虜になるくらいならお互いに殺しあうという集団自決もガマで起こっています。」
クロードさん「ジェノサイドでは多くの人が鉈で殺されました。なたで殺されるぐらいなら教会や学校で自分たちで死ぬことを決めた人もいます。同じような状況かもしれません。
第一次大戦後ベルギーの支配下に置かれたルワンダではもともと共存していた民族を区別する政策が行われ対立構造が生まれました。そして1994年、宗教や言語などに違いはない民族同士であるにも関わらず組織的な殺害によって多くの尊い命が奪われました。
戦争にいたるまでの政策、そして住民の間で起きた悲劇。クロードさんはかねてから沖縄とルワンダの歴史に共通するものがあると感じていました。戦後79年を迎える沖縄がどのように記憶を継承しているのか、平和教育のありかたを学びたい。それがこの島を訪れた理由です。
「一般の兵や住民の名前も刻まれていてどんな方々もここに記されているのが平和の礎のひとつの特徴」クロードさん「私たちは同じように生まれ同じように死んでいくそれを知っていたら殺し合いにはならないのではないか。世界は過去から学びきれていない。」
「30年前のルワンダを思い出すのは私にとって辛いことです。しかし私の証言は平和の重要性を強調するでしょう。」クロードさんは大虐殺が起こった背景に民族を分断する政策が長年続いたことのほかメディアによる扇動があったと述べました。
ルワンダの場合50年以上にわたって憎悪に満ちたメディアによって燃え広がる虐殺にいたる不和の種が蒔かれました。紛争中メディアは巨大な力となります。
「メディアの物語を受動的に受けるのではなく、意図を見抜き、真実を求め、信念を貫くことが不可欠です。ルワンダの大虐殺が遠い過去のように感じられるかもしれませんが、同様の悲劇は今日も続いています。歴史から学び断固たる行動をとらなくてはなりません」
来場者は「(経験した)人がいなくなってしまうのは、我々はいま起こっていて、ルワンダではこれから起こることだと思うので我々は先をいく世代としてできることはないかなと」
高校生「SNSでいろんな人が発信しているそれを簡単に信じて虐殺とかそういうことに最終的につながってしまうことがある。一人ひとりがそういう意識をもつことが大切」
「沖縄は平和を語る先輩だ」というクロードさん。わずかな訪問期間ではありましたがルワンダに戻ってからの活動に新たなヒントを得られたようです。
クロードさん「沖縄の人々が証言を集めて記憶を守り続けること、若い世代がそれを理解し平和について語り続ける取り組みが大切です。皆さんならば平和で明るい未来を築ていくれると私は確信しています。」
あわせて読みたい記事