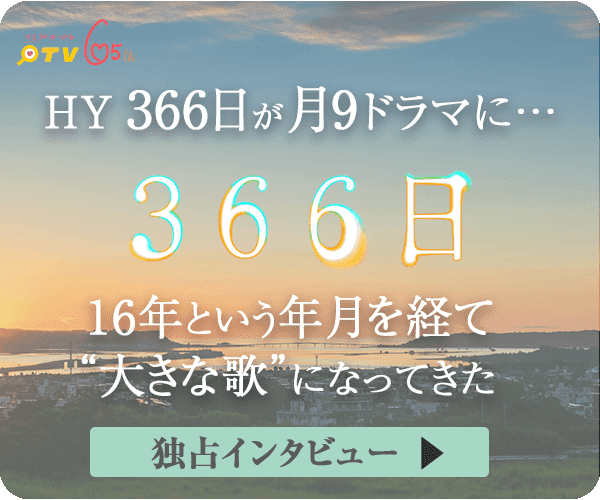沖国大ヘリ墜落事故から20年「記憶を風化させない」「基地問題に向き合い公平な負担を」
沖縄国際大学に、アメリカ軍の大型ヘリが墜落し炎上した事故から20年となりました。事故のあった沖縄国際大学では今年も集会が開かれ、記憶を風化させまいと、学生や卒業生、地域住民が集いました。
2004年8月13日、アメリカ軍の大型ヘリが沖縄国際大学の構内に墜落し、炎上しました。沖縄国際大学では墜落現場のモニュメントの前で集会を開き、安里肇学長は、「何も変わらない現状と今後が見通せない未来に大きな危機感を覚える」と話し、「事故の惨事の記憶を風化させてはいけません」と述べました。
また、学生の代表からは、基地問題を国民全体の事として考える必要があると述べました。
沖縄国際大学3年儀保裕一朗さん:
「本土の人にとって沖縄の基地問題は都合の悪い事だと思います。その都合の悪いことから目を背けないで欲しいのです。基地が必要だというのなら、基地問題に向き合い、公平な負担をしてほしいのです」
集会には事故当時の学生たちが参加し、当時の状況を振り返りました。
石垣から初めて集会に参加した慶田盛旬さん(当時沖国大2年生):
「ドドンという音が聞こえて、来たらヘリの中から操縦士が這いつくばって出てきて『ヘルプミー』と言って、そのあとに爆発があってという感じです。トラウマになって、苦しい時期もあったんですけど、忘れようというのが強かったので(来られなかった)
息子を連れて毎年参加する比嘉美香子さん(名護市)(当時2年生):
「お母さんが通っていた大学でこういうことが起きたというのが、事実としてあることはしっかり伝えたいなと思って毎年連れてくるようにしています」
息子の比嘉琉希さん(名護市):
「結局は基地があるままだし、オスプレイとかも飛び交っているし、何もかわっていないんじゃないかなと、なんか悲しくなってきました」
沖国大のヘリ墜落事故から20年が経過しましたが、この間にも普天間基地所属のオスプレイが名護市安部の海岸で大破したほか、普天間第二小学校にヘリの窓を落下させる事故を起こすなど、その危険性は放置され続けています。
宜野湾市の和田副市長は、「今なお普天間基地の全面返還という約束が守られず、市民の切実な願いが置き去りにされ続けている現状について、日米両政府及び全県民・全国民の皆様にもぜひ考えていただきたいと」とコメントし、一日も早い閉鎖・撤去を改めて求めました。
あわせて読みたい記事