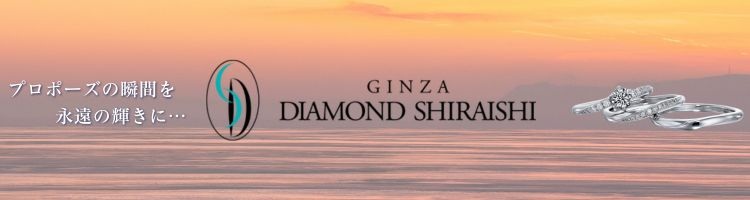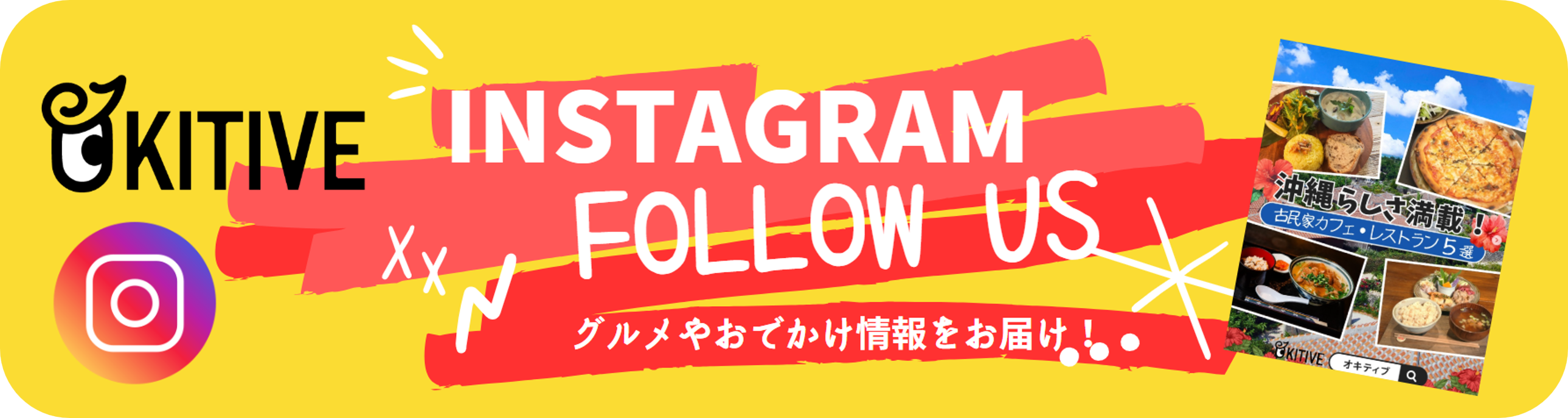エンタメ,タレント・芸人,テレビ
沖縄にテレビが来た!65年前、テレビマンたちの奮闘の歴史を描いたものがたり 脚本・ゴリさんインタビュー
エンターテインメントは調味料

—今回の物語を作っていく中で、沖縄の今まで知らなかったことに出会ったり、あらためて沖縄に向き直したような感覚はありましたか。
沖縄まで毎日飛行機でフィルムを運び込むというのは、やっぱり物理的な限界があるんですよ。飛行機が遅れたら放送が遅れるわけですよね。でもその中で、ただテレビ局だけが頑張っているだけじゃなくて、色んな企業の皆さんも含めて自分たちの利益だけじゃなくって、沖縄のために立ち上がるんですよ。政治に訴えかけ、日本政府に訴えかけ、九州から海底ケーブルを引っ張って広大な工事も成功させることにわけです。
僕は「復帰っ子」ですけれども、僕らの世代からはもうテレビ見えるのが当たり前。これまでの奮闘の経緯やありがたみに気付かずに育ってきてるんですよね。だからこうして過去の出来事を勉強させてもらったことによって、今のこの状況が当たり前じゃない時代があったんだっていうことを教えてもらえた。そんな良い機会を与えてもらったなと思います。
—ドラマを作っていく上での“ゴリらしさ”についてお話されていましたが、社会とエンタメ、あるいは社会と笑いの関係性について、ゴリさんはどんな風に捉えていますか?
社会って、良いことだけではないじゃないですか。悪い部分も当然あるんですけども、そういう社会の悪い面に真剣に向き合う人もいれば、嫌な思いをしたくないから見たくない人もいるはずなんですよ。
でも、そこに「笑い」という要素を入れると、見たくない聞きたくない人も興味を持ってくれるんです。その意味で、やっぱりエンターテインメントは“調味料”としてとても大事だと思うんですよね。例えば、ゴーヤーチャンプルーは嫌いだけれども、ダシかけたら食べられるみたいな(笑)。

—なるほど(笑)。卵でとじたらさらに食べやすくなりますもんね。
そうそう。そうやって苦味を和らげて食べられるようにする、という部分がやっぱりお笑いとかエンタメの役割でもあると思っています。だから、どうしても堅苦しいイメージになってしまう社会問題にエンタメを混ぜ込むことによって、食べられない・食べたくないという人の口元まで持っていける。
そう考えると、やっぱり良い関係じゃないですかね。もちろんエンタメはエンタメだけでもいいし、社会問題を伝えたり考えたりする報道も必要だけれども、それらを混ぜることによって、色んな人たちの“口に入っていく”ものなのかなと。
「当たり前」ができるまでの奮闘の歴史

—最後に、読者にむけてメッセージをお願いします!
朝起きたら当たり前のようにつけるテレビですが、先人たちの汗と涙の闘いによって、今の「当たり前」があるんだということを感じてもらいたいですし、このドラマを観ることでテレビ各社の社員さんに少し優しく接することができるんじゃないでしょうか(笑)。テレビマンが好きになるというか。
奮闘の歴史についても、OTVの番組ですけど、大きなことを成し遂げられたのはもちろんOTVだけじゃなくて他の県内のテレビ局の頑張りもあったんです!…ということを制作チームの人に何度も言われて(笑)、沖縄ってやっぱり横のつながりも大事にするんだな、と温かいものをもらいました。そんなことも感じてもらえればと思います。

あわせて読みたい記事