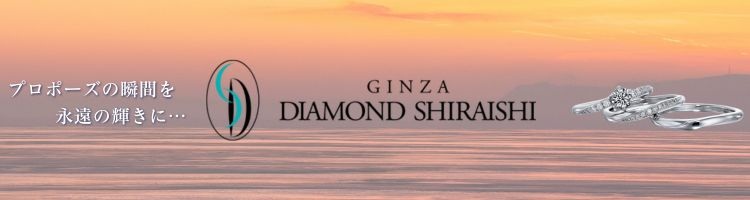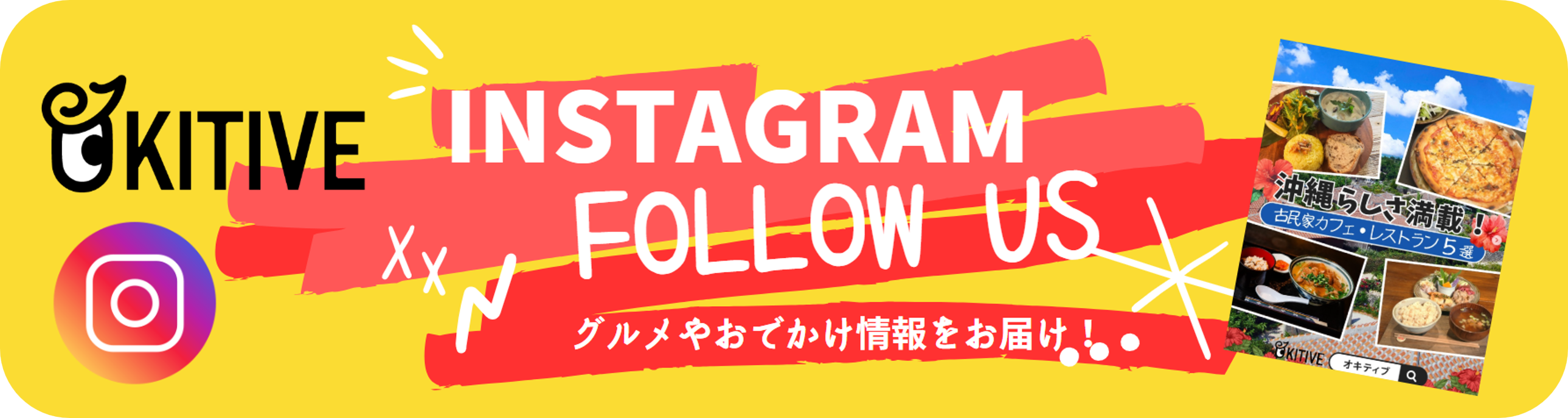コラム,暮らし
子どもがお手伝いしたくなるポイントは!?「片付けのゴールデンゾーン」工夫と片付けの仕組み作り
こんにちは!
整理収納アドバイザーの親富祖(おやふそ)いつみです。
「うちの子、片付けやお手伝いを全然してくれなくて困っている」
そんな声をよく耳にします。実は子どもは「やりたくない」のではなく、「どうやったらいいか分からない」ことが多いんです。
ほんの少し環境を整えたり、声かけを工夫するだけで、子どもは驚くほど意欲的になります。今回は 子どもがお手伝いしたくなる片付けや収納の工夫 を、実例を交えてご紹介します。
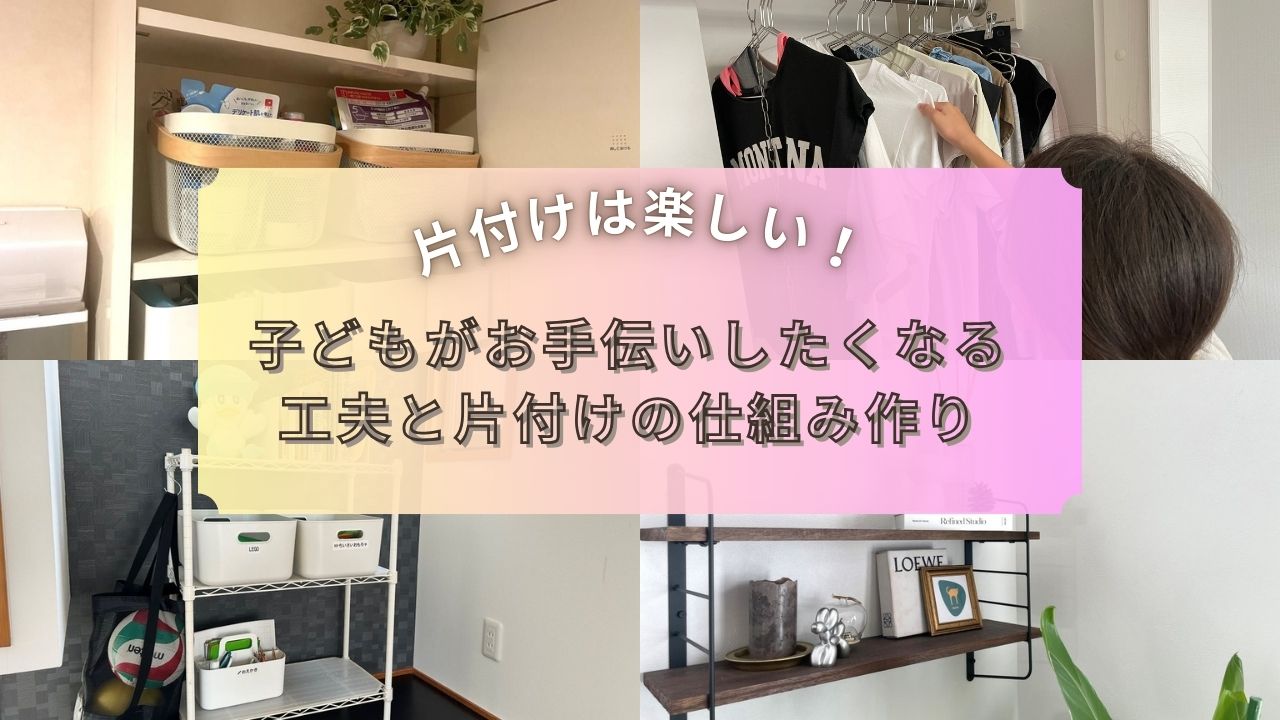
目次
① 子ども目線で高さや場所を工夫する
片付けや家事のスタートラインは「自分で出せる・戻せる」こと。大人にとっての便利さではなく、子どもにとっての使いやすさを優先するのがポイントです。
ここで意識したいのが 「片付けのゴールデンゾーン」。これは人が最も出し入れしやすい高さを指し、大人の場合は腰から目の高さ、子どもなら肩から腰の高さにあたります。この範囲に子どものよく使うものを置くと、自然に「自分でできる!」という気持ちが芽生えます。
例えば、コップやお皿を子どもの手の届く高さに置くだけで、「自分で用意できた」という自信につながります。おもちゃも高すぎる棚に置くと出すのも戻すのも億劫ですが、腰の高さに置けば遊びやすく、片付けやすくなります。さらに、重いものは下段に収納しておくと安心。安全面にも配慮しながら「自分でやってみよう」と思える環境が整います。
親にとっても「ママ取って~」と呼ばれるストレスが減り、子どもにとっては小さな成功体験の積み重ねになります。こうした工夫は、自主性や自立心、責任感 を育む第一歩になるのです。

② ラベルやイラストを使う

文字が読めない小さな年齢でも、イラストや写真のラベルなら一目で分かります。たとえば衣類収納に「ズボン」「くつした」「ハンカチ」と書いた文字ラベルをつけ、その横にイラストを貼っておくと、子どもは迷わずに片付けやすくなります。
おもちゃ箱や学用品の収納にも同じ工夫が効果的です。ランドセルの横にノートやえんぴつの写真ラベルを貼っておけば、「ここに戻せばいいんだ」と一人で判断できます。学用品ストックにラベルをつけておけば、なくなったときに自分で補充する習慣も育ち、翌日の準備もスムーズになります。
視覚的に分かりやすい仕組みは「どこに戻せばいいの?」という迷いを減らし、親の声かけが少なくても子どもが動ける環境をつくります。片付けだけでなく、お手伝い全般に応用できる方法です。
③ 仕組みをシンプルにする
大人はつい「きれいに分けたい」「細かく収納したい」と思いがちですが、複雑なルールは子どもにとってハードルが高くなります。
我が家の実例では、
おもちゃ:フタ付きケースではなく、ポンと入れられるオープンBOXに。
洗濯物:シワが気にならないタオルや下着は畳まずポイっと収納。
学校のプリント:机横のお手紙BOXに入れるだけで提出忘れ防止。
このように「箱に入れるだけ」「フックにかけるだけ」のワンアクションで済む仕組みなら、子どもにとって取り組みやすく習慣化しやすくなります。大人目線の“完璧収納”よりも、子どもが自分でできる“シンプル収納”を優先することで、お手伝いが日常に根づいていきます。
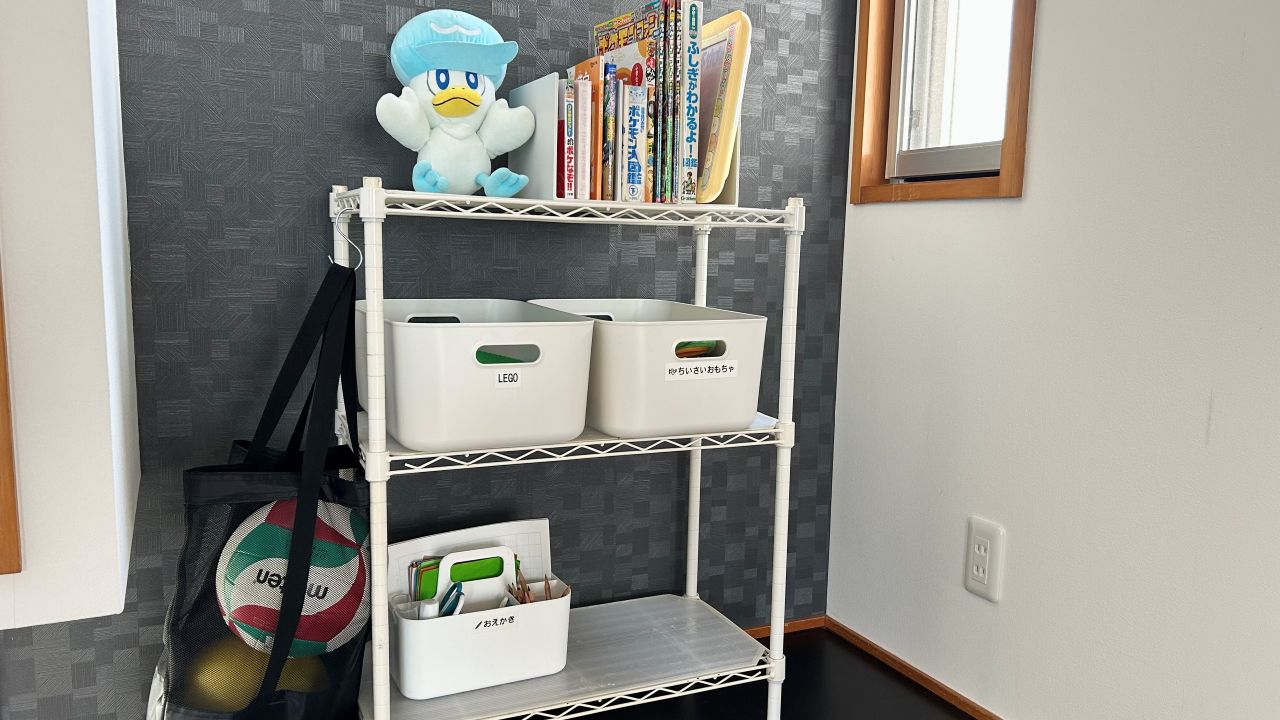
おもちゃ:フタ付きケースより、ポンと入れられるオープンBOXがおすすめ。

洗濯物:シワが気にならないタオル、下着は畳まずポイっと収納。
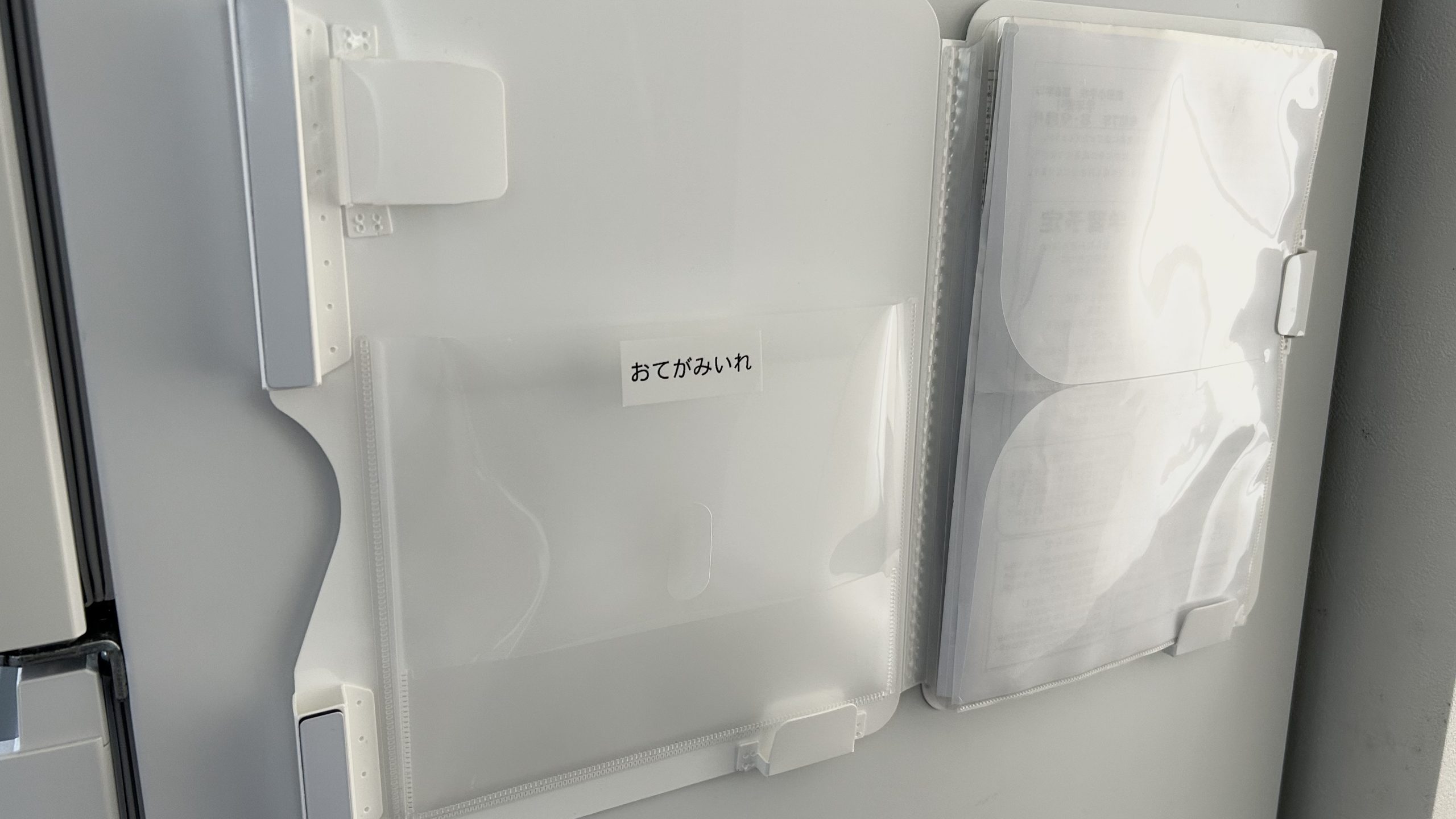
学校のプリント:お手紙BOXに入れて出し忘れ、提出し忘れを防ぐ。
④ 片付けを楽しい時間にする
片付け=イヤなこと、と感じてしまうと子どもは動きません。そこでおすすめなのが「遊びの延長」にする工夫です。
例えば「タイマー5分でおもちゃを片付けられるかな?」とゲーム感覚にしたり、「ママとどっちが早いかな?」と競争にしてみたり。子どもの遊び心をくすぐると、嫌々ではなく楽しみながら片付けられます。
また、音楽を流して「お片付けソング」をかけるのも効果的です。リズムにのって体を動かしながら片付ければ、自然と習慣化します。片付け=楽しい時間に変える工夫は、親子のストレスを大きく減らしてくれるでしょう。
⑤ ポイント、ご褒美を見つける
子どもは「がんばったね!」と褒めてもらえることが大好きです。小さな達成感を見える化してあげると、やる気が続きます。
たとえば「お手伝いをしたらシールを貼る」「ポイントがたまったら好きなおやつを選べる」など、ご褒美を取り入れる方法です。ただしご褒美は大げさでなくても十分。褒められた経験そのものが子どもにとって最大のモチベーションになります。
小さな成功体験を積み重ねることで、「お手伝い=当たり前」と自然に感じられるようになり、生活習慣の一部として定着していきます。
⑥ 年齢別のお片付け例
子どもの成長に合わせて「できること」を用意してあげると、お手伝いがぐんとスムーズになります。
未就学児(3〜6歳)
・テーブルを拭く
・脱いだ靴を揃える
・洗濯物をカゴに入れる
・おもちゃを箱に戻す
小学生低学年(1〜3年生)
・食卓の配膳(箸やコップを並べる)
・洗濯物を畳む
・玄関やお風呂掃除
小学生高学年(4〜6年生)
・サラダや炒め物などの簡単な料理
・掃除機をかける
・ゴミを集めてゴミ出し
年齢に応じた役割を与えることで「自分は家族の一員として役に立っている」と実感でき、責任感や自立心も育まれます。
⑦ まとめ
子どもにお手伝いをしてもらうコツは、特別な道具や大がかりな仕組みではなく、日常の環境を少しだけ子ども目線に整えることです。
手が届く「ゴールデンゾーン」に置く
できるだけシンプルに
楽しさを取り入れる
成功体験やご褒美でやる気を育てる
年齢に合った役割を与える
これらを意識するだけで、子どもが自分から動いてくれるようになり、親も「助かった」「ラクになった」と感じられるはずです。片付けやお手伝いは、子どもの自信や自主性を育む絶好のチャンス。ぜひご家庭に合わせて無理なく取り入れてみてくださいね。
あわせて読みたい記事