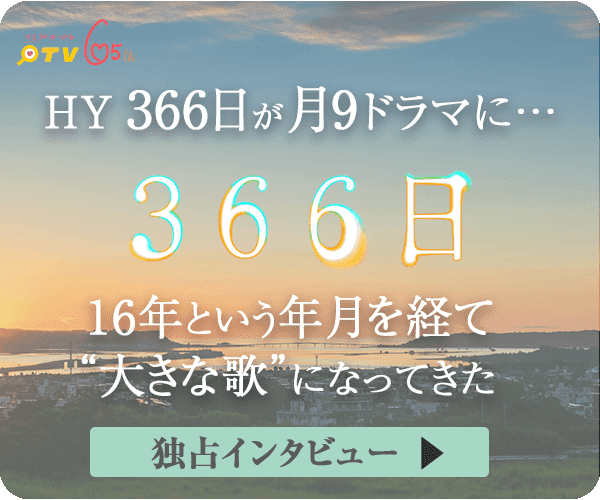エンタメ,スポーツ,地域,本島中部,沖縄市
キングス・桶谷大HCの“指導哲学”とは 礎となった「失敗」とNBA名将の一冊の本

プロバスケットボールBリーグの2022-23シーズン、琉球ゴールデンキングスが悲願の初優勝を遂げた。全60試合を戦う長いレギュラーシーズンで積み上げてきた「層の厚さ」を武器に、チャンピオンシップ(CS)では無傷の6連勝。シーズン終盤に多くのチームで主力の怪我が相次ぐ中、負傷で長期離脱する選手もおらず、全員でつかみ取ったチャンピオントロフィーだった。
高いチーム力を構築した最大の功労者は、桶谷大ヘッドコーチ(45)だ。能力に秀でたプレーヤーが多いキングスにあって、連係がうまくいかない時期も含めて多くの選手でローテーションし、個々に成長を促す戦い方を貫いた。確固たる“指導哲学”はどのように築かれ、昨シーズンのキングスの強さにいかに反映されていったのか。
その過程には世界最高峰リーグである米NBAの名将が自身のコーチング論を説いた一冊の本との出合い、そして、自らの「失敗」と真摯に向き合い、一人の指導者としてもがき苦しんだ時期があった。
目次
病に屈せず単身渡米 コーチの道へ
京都府出身。バスケ指導者だった父・良さんの下、小さい頃からバスケットボールをおもちゃ代わりに育ち、中学でバスケ部に入部した。しかし中学1年の夏、腎臓病のネフローゼ症候群を発症。高校まで入退院を繰り返し、満足いくまでプレーできず苦悶の日々を送った。
卒業後、コーチの道を志し単身渡米。ツテも英語力もなかったが、アリゾナ州立大学の多目的施設でシュート練習をしていた選手を毎日自主的に手伝った。心の距離を縮めたことで誘いを受け、晴れてチームマネージャーに。攻守に規律の厳しい米国のバスケを学んだほか、ディフェンスを重視するHCの方針は「得点が1点なら相手をゼロに抑えて勝てばいい」という信念を持っていた父のコーチングにも通ずるものがあり、守備から流れをつくる今の戦い方の素地が築かれた。
ちなみに、自身をチームに誘ってくれた選手は、後にNBAでプレーすることになるエディー・ハウス。シックスマンのスコアリングガードとして多くのチームで活躍し、2007-08シーズンにはボストン・セルティックスでNBAを制覇した名プレーヤーである。
その後、2005-06シーズンに旧bjリーグの大分ヒートデビルズのアシスタントコーチ(AC)に就いて指導者歴をスタートした桶谷氏。2008-09シーズンには、ジェフ・ニュートンとアンソニー・マクヘンリーを加えて一気に戦力アップしたキングスのHCとなり、参入初年度の前シーズンは西地区最下位だったチームを、いきなり頂点に導いた。
名将フィル・ジャクソンに学ぶ 「カルチャー」の構築へ

31歳にして、日本バスケ界に変革をもたらそうとする新興プロリーグで優勝を果たし、順調に滑り出したかに見えたコーチ人生。しかし、キングス2シーズン目で壁にぶち当たる。開幕直後こそチームは好調だったが、前シーズンでMIP賞を獲得した点取り屋の金城茂之、エースのニュートンが負傷離脱し、後半に失速した。
「1年目は勢いで勝ってしまって、まだ球団としてのカルチャーがなく、幹がグラグラの状態でした。シゲ(金城)がいなくなった時も、一人いなくなるだけでこんなに弱くなるのか、と感じるくらい。だから、誰かの力に頼り過ぎることなく、チームでシーズンを戦っていくスタイルを目指しました」
そんな時、自身の指導哲学に大きな影響を及ぼすことになる一冊の本と出合う。マイケル・ジョーダンを中心としたシカゴ・ブルズで1990年代にNBA3連覇を2度達成し、2000年代にもコービー・ブライアントらを擁するロサンゼルス・レイカーズで3連覇と2連覇を果たした名将フィル・ジャクソン氏のコーチング論をまとめた自伝「Sacred Hoops」である。
80年代後半、ブルズはジョーダンという強大な“個”への依存度が高過ぎて、チームとしての限界を露呈していた。しかし、ジャクソン氏がチームで攻める戦術「トライアングル・オフェンス」を導入。結果、周囲の選手のレベルが向上し、よりジョーダンの個人技が生きるようになり、無敵の王朝を築くまでに至った。桶谷HCと木村達郎GM(当時)は、定期的に2人で顔を突き合わせながら「Sacred Hoops」を読み合わせ、感想を言い合い、キングスが目指すべきチーム像を模索していった。
「日本では主力の7、8人くらいでローテーションをするチームが多かったけど、フィル・ジャクソンは当時から10人のローテーションを徹底していました。それはプレータイムを分散してケガ人のリスクを減らすためだけでなく、選手たちが『チームに参加している』というメンタルを保ち、やりがいを持続するためでもありました」
キングスは最終的にこのシーズンを3位で終えたが、「全員で戦う」というチームの“幹”を太く、強く成長させていったことで、個人の調子や離脱に結果が左右されにくくなり、桶谷氏と木村氏がカルチャーに据えた「毎年優勝争いをできるチームづくり」を体現。翌シーズンは準優勝、さらに2011-12シーズンには2度目の頂点をつかみ、桶谷氏はこのシーズンをもってキングスHCを勇退した。
“高い鼻”を折られた大阪時代 仙台で「変化」

その後は、本人いわく「失敗ばかり」だった。例に挙げたのは、15年から3シーズンHCを務めた大阪エヴェッサ時代だ。当時はフィル・ジャクソン氏が率いたブルズで、選手として3連覇を経験したビル・カートライト氏が大阪のアドバイザリーコーチに就任。「コーチは絶対に10人を使ってローテーションしなさい」などと助言を受け、キングス時代と変わらず全員で戦う戦術を用いていたが、別のところに落とし穴があった。
「当時は自分が考えているバスケットが日本で一番いいと思っていて、それをできないのは自分が悪いんじゃなくて、選手たちが悪いと思っていた。とにかくダメ出しが多くて、『これをやりなさい』という指示ばかり出していました」と振り返る。結果、能力に優れた選手は多かったが、Bリーグが開幕した16年から2シーズン続けて勝率は5割に届かず、CS進出を果たすことはできなかった。
選手との信頼関係が築けなければ、チーム力は上がらず、結果もついてこない。無意識のうちに高くなっていた鼻を折られ、初心に戻った。「選手たちとどう付き合うべきか。ヒューマンマネジメントがもっと大切なんじゃないかと考えるようになりました」。18年にHCに就いた仙台89ERS(当時B2)で、早速実践に移す。
メンタルコーチにフロント入りしてもらい、選手に自信を植え付けることや、チームづくりにより参加させる方法を模索した。その一環として、練習の前後に選手たちが2人1組となり、目標や達成できたことを話す「ペアトーク」を導入。すると、徐々に練習や試合での選手同士のコミュニケーションが増え、ディフェンスを中心にチーム力が向上した。就任1年目で前シーズンから勝ち星を2倍近くに伸ばし、40勝20敗の東地区2位。さらに翌シーズンは地区優勝と結果を出した。
その過程で、選手たちとの向き合い方にも変化が生まれた。
「選手たちが何をやりたい、どう成長したい、ということを尊重し、それを促していく指導になりました。すると、選手は自分たちで考えてやっているからチームにコミットしている感覚をより持つことができます。それが個々の成長につながり、勝ち負け以上にチームのカルチャーをつくる上ですごいプラスになりました」
チームとして全員でどう戦うか、そして、個々の選手とどう向き合うか。様々な経験を糧に指導者として成長し、2021年に再びキングスのHCに就いた。
序盤戦はまとまらず 時には選手と対話も

2021-22シーズンはレギュラーシーズンで49勝7敗とB1の歴代最高勝率(当時)を記録したが、ファイナルでは田代直希、牧隼利、渡邉飛勇、並里成を負傷やコンディション不良で欠き、宇都宮ブレックスに2連敗。2022-23シーズンは、並里、昨シーズンベスト5のドウェイン・エバンス、帰化選手の小寺ハミルトンゲイリーが退団し、ジョシュ・ダンカン、松脇圭志、ジェイ・ワシントン(昨年12月退団)を加えた。
桶谷氏は「前のシーズンの最後は本当に人がいなくて、ある程度それぞれの役回りが決まっていました。でも、このシーズンは田代、牧、飛勇が戻ってきて人が多いので、アプローチの仕方が変わるということは初めから思っていました」と開幕前を振り返る。そこで掲げたテーマの一つが“ポジションレス”だった。各プレーヤーに様々な役割を求めて個々に成長を促し、チームが高いレベルで融合する「層の厚さ」を目指した。
迎えた開幕2連戦は宿敵・宇都宮に2連勝と好スタートを切った。しかし、徐々にほころびが見え始める。コー・フリッピンが11月に日本代表に招集される前後になかなか連係がうまくいかなかったり、田代や松脇、11月半ばに復帰した牧らの調子が上がらなかったりして、特にセカンドユニットがコートに出ている時に強みであるボールムーブメントが停滞する時間帯も散見されていた。
そんな中、チーム内には選手の起用方法に対する不満や、より多くのプレータイムを求める声もあり、なかなか一つにまとまらない時期があったという。それでもローテーションしながら戦うことを重視し続け、時には選手と深く対話した。
「特にセカンドユニットは出場時間が短い中で、それぞれの選手がいろいろな思いを持ちながらプレーをしていました。起用方法に不満を抱える選手に対して『同じプレーヤーがずっと出ていたら相手は守りづらいけど、違う個性がある選手が多くいれば、それはチームにとってプラスになるから』と、ローテーションしながら戦う意義を説明したこともあります」
「昔なら有無を言わさず怒ってるだけだったかもしれませんね」と冗談ぽく笑う桶谷氏。仙台時代に培った「選手を尊重する」という姿勢は、ここで生かされた。
「風、来てますよね」終盤の島根戦で優勝の感触

12月に入ると、「セカンドユニットで点数が止まっていた」という理由で得点力の高いアレン・ダーラムにベンチスタートを求め、本人も「それで勝てるなら自分は何でもやる」と快諾。さらに牧がセカンドユニットにおけるハンドラーとして存在感を高め始めると、少しずつチーム全体として安定感が生まれ始める。互いの個性に対する理解も進み、それに比例して勝率も上がっていった。
最終的に優勝できる感触をつかんだのは、今年4月12日に当時西地区1位だった島根スサノオマジックとアウェーで戦った51戦目だという。この試合は11人が出場し、攻守ともに誰が出ても高水準のプレーを続け、87-72で快勝した。
「僕がコーチをしていて、選手に必要だと思うことは『自信を持って判断すること』『チャレンジすること』『迷いがないこと』ですが、島根戦ではこの三つがバランス良く出ていました。この勝ち方ができるなら、どのチームにも勝てると思いましたね。試合後に、(岸本)隆一が『これ、風来てますよね』って言っていたのを覚えています。選手たちも『キングスの戦い方はこれだ』と感じたと思います」
その後、残りのレギュラーシーズンを8勝1敗で終え、CSも無敗で戴冠したことからも、その時の感触が間違いではなかったことが分かる。特に千葉ジェッツとのファイナルでは、ベンチポイントで第1戦から順に45対4、45対17と圧倒。優勝を決める第2戦の第4Qは、ほとんどの時間を牧、松脇、フリッピン、ダーラムのセカンドユニットがプレーし、シーズンを通して構築してきた「層の厚さ」を象徴した。
桶谷氏はよく「ゲームの最後に誰が出ているかが一番大切」と言う。便宜上、「セカンドユニット」という表現は使うが、ベンチスタートのメンバーは力が劣っているという認識はない。フィル・ジャクソン氏から学んだ、最低でも「10人でローテーションする」という戦い方を貫き、CSでは誰が出てもチーム力が下がらない強さを手に入れた。
新たなカルチャーは「成長の“余白”があるチーム」

bjリーグとBリーグの両方で優勝を果たした、ただ一人のHCとなった桶谷氏。2022-23シーズン、コーチとして自らの成長した点を問うと、柔らかい笑みを浮かべながらこう答えた。
「それは分からないですね。ただ、僕は人が成長してるのを見るのがうれしいんです。昨シーズンは若い松脇や牧らがしっかり仕事をしてくれたし、コーチ陣もすごく成長しました。そういう意味では、勝ち負けで一喜一憂していた昔とは見ている観点が違うかもしれませんね」
成長を重視する姿勢は、メンバー構成にも色濃く影響を与えている。例えば、昨シーズンからファンの間でよく話題に上がる「なぜキングスはポイントガードが少ないのか?」という疑問に対する答えである。理由はこうだ。
「少ないからこそ、牧や隆一、今村もポイントガードの仕事をしないといけなくなるんです。確かにいいガードの選手がもっといれば戦力として向上するかもしれませんが、シーズン中にみんなが成長するスペースがあることの方が大事なんです」
確かにチームの“余白”(スペース)は個々の役割を広げたり、プレータイムを伸ばしたりして、成長を促す。昨シーズン、ガードとしての能力を伸ばした牧や、アシスト数を増やした今村佳太らを見れば一目瞭然だろう。ダンカンが抜けた新シーズン、新加入のヴィック・ローはガードで起用することもできるため、昨シーズンは出番が限られていた渡邉やタマヨもビッグマンとしての出場機会が増え、より個人としても成長していく可能性がある。
全員で戦い、常に優勝争いに絡み、個々が成長できるチーム。それが、キングス。多くの苦難と栄光を経験してきた桶谷氏の指導者としての成長と共に、キングスのチームカルチャーがより厚みを増している。


2024年5月31日15時45分〜 沖縄県内のTV 8チャンネルにて放送!!
沖縄テレビ(8ch)では、5月31日(金)15時45分から琉球ゴールデンキングスのシーズンを振り返る特別番組を放送します!
ぜひご覧ください!
あわせて読みたい記事